YCL Interview〈⽂化圏を拡張する実践者たち〉は、⼭梨県で活躍する⽂化芸術の担い⼿に迫っていくインタビュープロジェクト。今回はアーティストの滞在制作を受け入れている施設のうちArtist In Residence Yamanashi [AIRY]、SAIKONEON、GASBON METABOLISM、6okkenの4者が集まった。
テーマは「アーティスト・イン・レジデンス」。アーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」)とは、アーティストが一定期間ある土地に滞在し、常時とは異なる文化環境で作品制作やリサーチ活動を行うこと。AIRの目的には優れたアーティストの創作・生活支援、地域文化の振興、異なる文化を持つ国や地域とアーティストとの交流、情報や人的ネットワークの促進などがある。一言でAIRと言っても、それぞれの特徴やキャラクター性は多種多様。4者がスペース運営に至った経緯や大切にしている理念などを、前編・後編に分けて紹介していく。
前編はこちら
西野慎二郎
ガスアズインターフェイス株式会社 代表取締役
1996年に新しいアートとデザインのアイデアを世界中から集める媒体として「GASBOOK」創刊。2004年に国内外のクリエイターと社会・企業を接合するプラットフォームとして同社設立。2006年より東京 西麻布で「CALM & PUNK GALLERY」を運営している。アートの複合施設「GASBON METABOLISM」を2022年8月に始動させた。
GASBOOK: https://store.gasbook.tokyo/ja
CALM & PUNK GALLERY: https://calmandpunk.com/
GASBON METABOLISM: https://www.instagram.com/gasbon_gasbook/
筒|tsu-tsu
ドキュメンタリーアクター / 6okken 共同代表
神楽や日本舞踊の手習いから得た「筒(つつ)」という身体感覚を手がかりに、実在の人物を取材し、演じる一連の行為を「ドキュメンタリーアクティング」と名付け、実践する。他方で、2022年から山梨県河口湖町にて、アーティスト・ラン・レジデンス「6okken」を設立・運営する。主な受賞に、第28回CGC最優秀賞、やまなしメディア芸術アワード山梨県賞、Forbes Japan 30 under 30 2023など。
Instagram: https://www.instagram.com/tsu_tu_/
山口みいな
アーティスト / 6okkenメンバー
多摩美術大学大学院絵画学科油画専攻修了。線を引く行為—身体の思考—を通して、他者との対話や自己表現を探求する。2023年より「6okken」に居住し、エクスペリメンタルキャンプの主催など、合宿企画のディレクターを務める。主な受賞に「多摩美術大学卒業制作展優秀作品賞/福沢一郎賞」。主な発表に「ドローイングセッション」、「ユンクス・エフスス・スピラリス」(galleryseana、2023)、「阿寒AINU ART WEEK 2024」参加など。
Instagram: https://www.instagram.com/miinayamaguchi/
6okken: https://www.instagram.com/6okken/
GASBON METABOLISM(北杜):研ぎ澄まされた感覚で刺激を受けてもらうことで、自分の発展や進歩に実感を持てるような経験を提供したい

GASBON METABOLISM(以下、GASBON)を始めた経緯を教えてもらえますか?
西野:東京でCALM & PUNK GALLERY(以下、CALM & PUNK)というギャラリーを15〜6年運営していましたが、コロナ禍の時に「誰も来てくれない」と寂しい思いを募らせていました。そんなときに30年一緒に働いていた共同経営者が鎌倉から山梨に引っ越すことになり、毎年2〜3回遊びにくるようになったんですよね。来るたびに天気が良くて妻と「ラッキーだったね」と話すくらい八ヶ岳が綺麗に見えたり、仲間と時間を過ごす中で「なんていいところなんだ」って気持ちがどんどん募っていったり。GASBONを始めたのはそういうことが続いた結果です。実際に運営を始めてみたら、CALM & PUNKで待ってるよりも何十倍、何百倍とたくさんの人に会えるんですよ。始まってちょうど2年が経ちますが、1年で1万人の来場者が来てくださるようになりました。来てくれた人にはメールマガジンを送っていて、そこから「レジデンスはやっていないんですか?」といった問い合わせや、「ポートフォリオを持っていっていいですか」みたいなコミュニケーションが始まっています。

GASBONは滞在している人が運営側に回る場合があるのもユニークですよね。アーティストとの関わりについて教えてもらえますか?
西野:GASBONはアートの複合施設で、スタジオ利用ないしは倉庫利用の会員さんがいます。他には、朝8時から17時までは運営スタッフとして入ってもらって日当を出し、17時を過ぎたらアトリエに入ってもらうという関わり方の人もいます。長いと9ヶ月くらい*滞在するアーティストさんもいます。場所の使われ方としてはギャラリー、倉庫、スタジオ利用に加えて、ビール屋さんがテナントとして使っていたり、知り合いのカメラマンさん・スタイリストさんの紹介による撮影地として利用されることもあります。やっぱりシンパシーがある人たちの推薦っていろんな方と関わっていく上で一番ありがたいし大切にしていきたい。僕たちはお酒を扱っていたり音を出すイベントを開催したりするので、地域の方たちを含めて関わる人とコミュニケーションをしていないと生きていけない前提があると思ってます。
*2024年10月時点。現在は年間最大6ヶ月、一回の滞在では最大4ヶ月。
筒:この間GASBONのイベントに行った時、子供がいっぱい来てるし、地元のお祭りみたいになってて感動しました。地元の人とはどうやって関わってきたんですか?

西野:地域にお住まいで様々お手伝いいただいている方がすごい親切な方で、その方が地域についていろんなことを教えてくれました。あとは地域の元村長さんが近くに住んでいらっしゃるので屋台を一緒にやったり、大工さんはなるべく実際に通って絡んでもらえる人にお声がけして壁塗りワークショップを大工さんの子供と一緒にやったり。その子達が小学校でGASBONでのことを喋ってくれるんですよね。僕たちと関わってくれる人たちに、コンスタントに頼るのが肝だった気がします。
今後、GASBONとしてどんなチャレンジをしていきたいですか?

西野:僕はGASBONを社会実験のアイデアとしての乗り物だとしか思っていません。だから僕のアイデアを誰かが引き継いでくれれば、30年後に別の誰かが引き継いでくれるようになる。たぶんアートや文化に関わる上で、その流れの中で大きな包摂性とか自然との関係みたいなことを語る際に、ベクトルの1つとして人ではなくアイデアの方が流れていることを知るのも大切だと思うんです。そのことを1番明確に指し示してくれるのが、拡張した部分のアイデアをシャープかつ自信を持って見せることができるアーティスト。そんなアーティストたちの、20代の自由さから50代の生活レベルが変化するところまで、それぞれのライフステージに対応していきたいです。試し住みでもいいから山梨を経験してもらいたい。
あとは美しい景観がこれ以上荒れていかないよう守っていきたい。もちろん中には僕と同じようには考えていないアーティストもいるけれど、そういう違いはお見合いみたいなものだと思ってます。ここは毎日が実践の連続。目の前に広がる状況をダメだととるのか、面白いととるのかの違いですよね。ただ、制作をメインの目的に据えた時に、快適さは必ずしもベストではない。快適さや親切さの上に、人間関係や他の人の作品などから受ける刺激があるのが大事だと思います。場所の適性を判断して、アーティストに研ぎ澄まされた感覚で刺激を受けてもらうことで、自分の発展や進歩に実感を持てるような経験を提供したいと思っています。
6okken(河口湖):作品発表以外で表現を社会と繋ぐ1つの形

6okkenはどのような経緯で始まったのでしょうか?
筒:自分が作家としての活動を続けていくための環境を自分で用意したいと思ったのが始まりです。6okkenを始める前から都内でシェアハウスを運営していたのですが、僕がアートから影響を受けたのは現代美術として語られるものではなく、何か1つのものに向き合い続ける姿勢でした。6okkenが定義する「アーティスト」とは美術家や音楽家に限らず、その人が手放したらこの世から消えてしまう「俺しか気づいてないんじゃないか?」みたいなものに向き合い続ける姿勢を持っている人たち。6okkenはみんながそういうものに向き合い続けるための環境をつくる実験をする場所だし、そのやり方を共有する場所です。
山口:私は設立メンバーではなく、6okkenで企画をやるようになったのが6okkenに関わり始めたきっかけです。ものを作ってる人、ものを作ることに興味がある人が集まったり話し合ったりできる場をつくりたいという思いでシェアスタジオを運営しているのですが、そこは個人の場所がたまたまシェアされているという感じが強く、みんなで時間を共有してるという意識はあまりない。定期的にものをつくることに興味がある人たちと一緒にい続ける場所が欲しいと思っていた時に山梨のいろんなスペースを回ったんですよね。発表のためだけではなく、自分のアイデアや考えを直感的に実践できる場をつくりたいと思い、いくつか6okkenで企画をやった後にメンバーになりました。
6okkenには14人のメンバーがいますが、集団としてどんな理念を大切にするとか、どう運営していくかとか、そういった方向づけはどのように行なっているのですか?

筒:関わり方はそれぞれ違うし、何でお互いがつながっているのかも人それぞれ。なので、意思決定のイニシアチブを持ってるのはその中の数人だったりします。組織として特定の目的が強くあるというわけでもなく、さっき話した「自分の信じてることを続けられる状況の方が今よりもいいよね」みたいな意識をなんとなく共有している感じで、コレクティブというよりもサークルの方が近い運営体制かもしれません。
山口:今は企画運営や現地管理はほぼ無償のボランティアでエネルギーをかけているのが現状です。お金は得られないけど、自分のやってみたいことをやれるというメリットを感じて人が集まっています。いまは若いからできるけど、組織としてお金を得られないと活動が持続的になっていかない。これからは旅館業を申請して6okkenとしてお金を作っていこうとしています。
14人のメンバーで考える6okken内の意思決定プロセスなど、関わった人にしかできないような経験もあると思います。そういった情報はどこまで外に開いていこうと思っていますか?

筒:密にコミュニケーションをとるメンバーは14人から増やすつもりはあまりないので、河口湖の6okkenが大きくなっていくというよりも、6okkenのやり方を参考にして、それぞれが自分たちの場所でやって欲しいなと思っています。一方で、実際に行われた意思決定のプロセスなどはもっと手軽に共有できてもいいなと思うので、もっと手軽に参加できる方法を模索したいし、伝えられる企画をやっていきたいです。
山口:いまの6okkenはいろんな企画が動いていますが、実際にイニシアチブをとるメンバーは企画ごとに違うんですよね。このやり方は結構やりやすくて、「やっぱこれ助けて」と言い合える関わり方ができています。でも、その状態になるまでのプロセスが全然公開できてない。みんなが日々6okkenでやってることも全然公になっていないので、それをどうアウトプットしていくのかは考えなくてはいけないと思ってます。
レジデンスという機能は、自分たちの活動にとってどんな意味を持っていると思いますか?

筒:今は狭義の意味でのアートの意味合いが強くなって、発表する機会が展覧会とか芸術祭とかしかない。僕は人の多様性に比べて発表のフォーマットが少なすぎると感じているので、レジデンスは作品発表以外で表現を社会と繋ぐ1つの形だと思ってます。アートって生きるために必要なものとかそういう類のものだと思ってるので、1泊2日単位で同じ時間を共有することによる別の見せ方を増やす機会にしていきたいです。
山口:山間にあって、庭があって、近くまで鹿がおりてきちゃうような裏山があるような6okkenの環境だったから生まれるもの、ことって結構あって。長い時間をかけてたくさんの会話をすると、新しいアイデア・表現・思考が滲み出てきたりするんです。レジデンスはいろんな要素がアーティストに変化を与えていると思います。
筒:1人1人個別の視点があって、本当はそれらを1つの方向にまとめる必要はない。そのことを証明するのがアーティストという姿勢だし、アートの意味はわからなさそのものだと思ってます。日常の中にわからなさってあるよね、ということを浮き彫りにするための方法として僕はレジデンスを選んでいるのかもしれません。
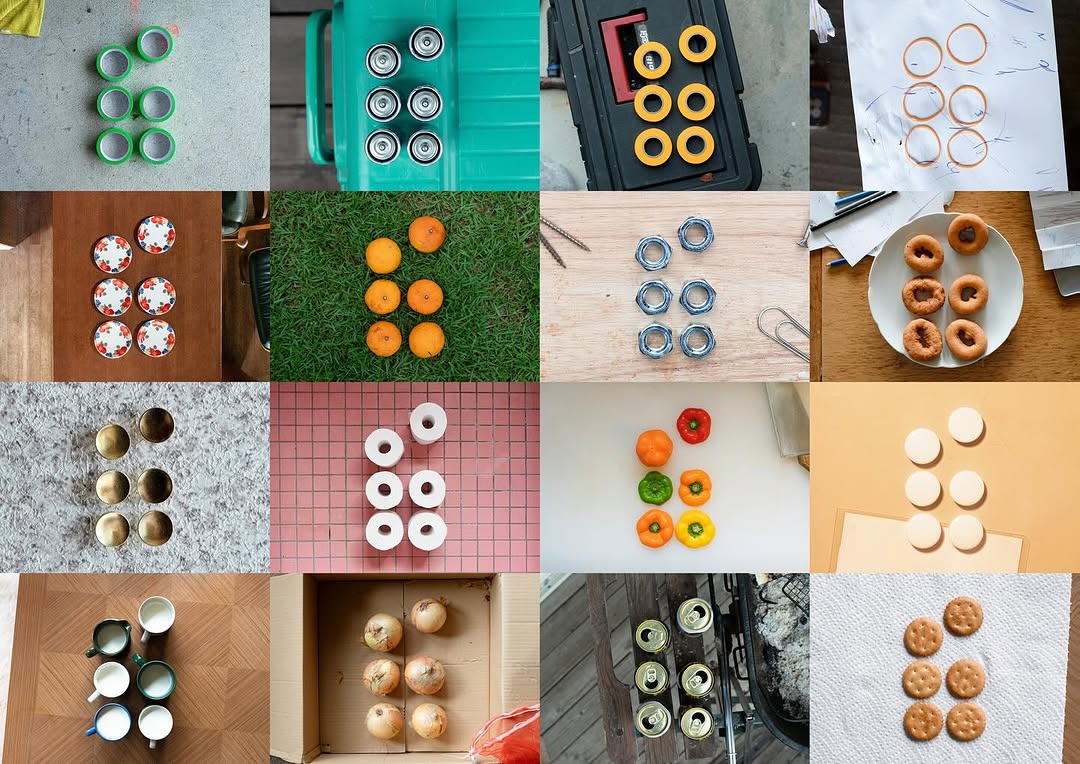
山口:自分は美大出身だったからこそ、6okkenは美大じゃない人たちと関わる初めての場所になりました。アートをやっていない人にどうアートを開くかを考えていた時に偶然来ていた人と一緒に絵を描いたりして。「こういうこともやっていいんだ」と気づいて、自分の活動ががらっと変わる感じがしました。
坂本:みなさんの話を聞いているとそれぞれスタンスが違う感じが面白いですね。私は「なんとかしなきゃ」という愛憎でAIRYを始めたけど、「いいじゃん、山梨動いてるじゃん」って気持ちになりました。これからは、自分が動かしているAIRYという「乗り物」のことをどんな風に伝えていくのかを考える時代になっていくのかもしれないですね。
「ここは毎日が実践の連続。」家の数だけ独自の空気が広がるように、それぞれのAIRで広がる景色も特徴も多種多様。AIRの魅力が自由さにあるからこそ、AIRはいろいろな人が県内を訪れるきっかけになっているのかもしれない。


